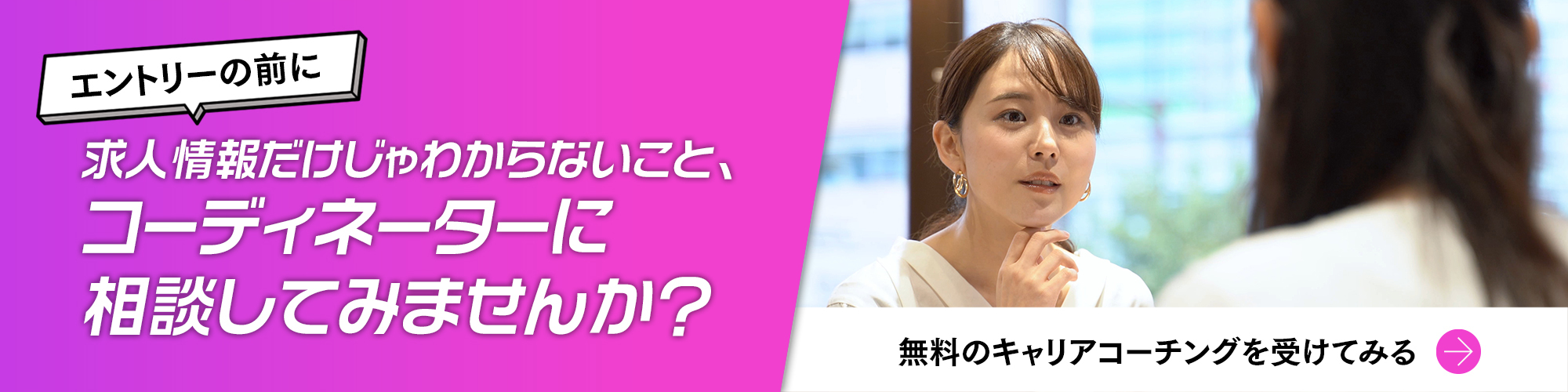| 雇用契約期間 | 雇用期間:無期(アルバイト、業務委託での採用も相談可能です。) |
【京都】「100年先もつづく、農業を」野菜提案企業オープンポジション

この求人のキーワード:
若手歓迎・スタッフ育成意欲のある組織 自然と人の調和、無理のない持続可能な社会 社会的インパクトを追い求める 環境・自然 農林水産 食・ライフスタイル ソーシャルビジネス・NPO サステナブル・環境・生物多様性 SDGs今は募集してない役割だけど我こそは!という方向け職種に縛られないオープンポジション募集
私たちの仕事について
坂ノ途中では、「100年先もつづく、農業を。」というビジョンのもと、環境負荷の小さな農業に取り組む人たちを増やそうと、事業に取り組んできました。
農業って本来、とても長い時間軸で捉えて語られるべきものです。人類は農業を始めて以来、1000年とか2000年といった長い時間をかけて土中に炭素や栄養分を蓄積したり、あるいは過度の放牧や地下水を汲み上げつづける(過灌漑)ことによって塩害を招き農地を使えなくしたり、そんなことを繰り返してきました。
現代農業は日々進化しているのだけれど、その進化は短期的な収量最大化、省コスト化を目指しているように見えます。想像力の及ぶ範囲が、狭くなっているのではないかとも思います。未来や他者に恩恵が及ぶような智慧や、金銭に換算できない価値あるものが失われ、短期的に自分自身が経済的な恩恵を受けられるようにという考え方が都市や工業から農村、農業へ持ち込まれ広まってきたとも言えます。
その結果、農業のエネルギー効率は悪化しているし、農林業の多面的な価値は軽視され、地域の余剰資源を循環させるよりも化学肥料を輸入してきたほうが手間もかからないし安上がりだという発想になります。
このままでは「たった」100年さえ続かないかもしれない。
坂ノ途中では、1000年も先のことはちょっとよく分からないけれど、せめて100年先くらいまでは想像しながら、それくらいの近い未来には責任ある生き方をしたいと思っています。
≪事業を進める際の、指針≫
1.環境負荷の小さい農業を広める
2.多様性を排除しない流通のしくみをつくる
3.ブレを楽しむ文化を育む
※詳細は、会社HP上の「私たちの考え」をぜひご覧ください。
https://www.on-the-slope.com/corporate/about/
●「こんな貢献できるよ」我こそは!と手を挙げるオープンポジション
坂ノ途中での仕事に興味があるけど、どの職種で応募したらよいか分からない、坂ノ途中で活躍できそうな圧倒的強みを持っている、今は募集してない職種だけど我こそは、という方を対象に、職種に縛られない応募もオープンポジションとして受け付けています。後述の応募方法をご覧いただき、正社員、アルバイト、業務委託など雇用形態の希望を明記の上、ご応募ください。
例)
・ 事業と社会的インパクトの拡大を押し進めるシニアマーケター
・ 出荷業務の最適化を図るオペレーション改善担当
・ より満足度の高いOnlineShopをつくり上げる商品企画担当
・ 顧客ロイヤルティの向上につなげるカスタマーサポート など
募集要項
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 契約期間 |
|
| テーマ | 環境・自然 農林水産 食・ライフスタイル |
| 職種 | 事業推進 |
| 組織形態 | 営利企業 |
| その他のキーワード | ソーシャルビジネス・NPO サステナブル・環境・生物多様性 SDGs |
| 対象人材像 |
●坂ノ途中のことを「自分事」として捉え、主体的に動ける方
|
| 応募資格 |
・「対象となる人物像」を満たしている方
|
| 歓迎条件 |
≪歓迎スキル・経験の例≫
|
| 新卒エントリー |
OK
|
| 未経験者エントリー |
OK
|
| 勤務地の住所 |
京都府京都市南区上鳥羽高畠町56 |
| 勤務地の詳細 |
近鉄十条駅から徒歩10分
|
| 勤務形態 |
一部リモート勤務OK |
| 勤務時間 |
9:00-18:00(休憩1時間)など |
| 給与 |
月給 259,700円〜457,100円 |
| 給与詳細 |
月給の内訳として
・経験や能力によって応相談
(参考情報)
|
| 福利厚生 |
・社会保険完備
|
| 受動喫煙防止対策 |
屋内禁煙 |
| 休日・休暇 |
・完全週休2日制
|
| 選考プロセス |
応募フォームから必要事項を送信
※こちらの求人情報は、NPO法人ETIC.の人材紹介サービスによって募集している案件です。書類選考や面接などは、坂ノ途中採用担当者のほかETIC.コーディネーターも担当いたします。あらかじめご了承ください。 |
代表者メッセージ
コーディネーターからの推薦コメント

企業・団体概要
- 設立: 2009年07月
- 代表者名: 小野 邦彦
- 従業員数: 180名
- 従業員数の詳細: パートアルバイト含む
- 資本金:
-
事業内容:
新規就農者を中心とした提携生産者が栽培した農産物の販売
環境負荷の小さい農業を広げるためのあれこれ - WEB: https://www.on-the-slope.com/corporate/
- 住所: 京都府京都市南区上鳥羽高畠町56









.png?disposition=attachment)